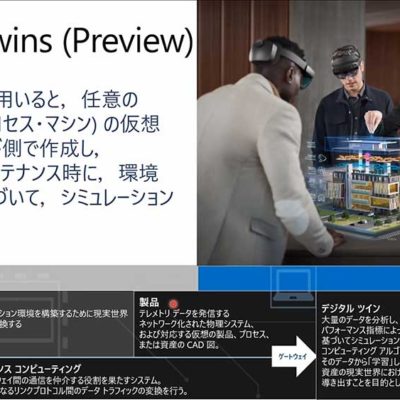06.18

【World MR News】トークイベントVR未来塾オンライン「Withコロナ時代におけるVRの可能性を語る vol.1」レポート
VR未来塾は、5月19日にオンライン・トークイベント「Withコロナ時代におけるVRの可能性を語る vol.1」を開催した。新型コロナウィルスの影響で、外出自粛やソーシャルディスタンスといった行動制限があるなか行われた、今回のイベント。こうした時代だからこそ活用できるVRについて、ゲストを招きトークイベントが実施された。
今回登壇したのは、電通 アクティベーションソリューションセンター インテグレーション推進部 ディレクターの足立光氏、ヤフー Developer Relationsの水田千惠氏、360Channel 代表取締役 社長の中島健登氏、テンアップ代表取締役 典和進学ゼミナール代表取締役の金谷建史氏の4名で、モデレーターは同イベントを主催する染瀬直人氏だ。

「ニューノーマル」をトリガーにVRを大衆化していきたい
足立光氏からは、「コロナが未来を持ち込んだ」というテーマでVRに関連した様々な事例紹介が行われた。
コロナ禍の元、生活を一新していかなければいけないということから「ニューノーマル」への適応が提案されている。マイクロソフトのCEOであるサティア・ナデラ氏は、「この2ヵ月で、2年分のデジタルトランスフォーメーションが起きた」と述べている。

日本でも学校が休みの間オンライン授業が行われているが、中国はさらに進んでおり小~高校生の教育従事者は、日本の10倍ほどとなっているのだ。eスポーツなどでゲームも注目を集めているほか、オンラインエクササイズのサブスクリプションサービスである「Peloton」が、1~3月期に66パーンセントも増収し、「おうち時間」の良い影響を受けている。
コロナ禍の業界背景には、行政やクライアント、メディアなどは様々な局面と接点でデジタルトランスフォーメーション化が強いられている。そうした中で、やらざるを得ないという状況からハードルが取り除かれていっている形だ。そのため、足立氏が所属する電通にも様々な問い合わせが来ているという。そこで自社開発にとらわれず、スピードを優先して様々な課題解決に取り組んでいるそうだ。
テレワークやオンライン会議が日常的になってきた中で感じることは、場所には依存しないがVRでは空間に依存する社会が起きている。課題としては、空間の再定義によってスポーツや観光、エンタメ業界の新たな楽しみ方をデザインしていくことだと足立氏は語る。
その中のひとつの手法として、VRも含まれている。中でも足立氏がお気に入りなのはファーストエアラインのサービスで、3つの旅行体験と料理が楽しめるというものだ。

バーチャルが広がっていくことに伴い、フィジカルな体験の付加価値も一層必要となってくる。足立氏は「ニューノーマル」に向けて、VRをトリガーに大衆化をしていきたいと考えている。
バーチャル展示会とVRライブ配信の可能性
中島健登氏からは、「バーチャル展示会とVRライブ配信の可能性」というテーマでセッションが行われた。中島氏が代表取締役を務める360Channelは、VR動画のプロが2000本以上ものコンテンツを提供しているサービスだ。
今回のお題でもある「展示会VR」については、コロナ禍の影響もありかなり問い合わせがあると中島氏はいう。元々ニーズはあったが、それがこの状況で顕在化した形だ。

過去の事例としては、「ウエルネスフェスタ2019」で、イベントをブラウザのオンライン上で見られるようにしている。技術的にはGoogleマップのようなものだが、ユーザーが見ているポイントがわかるほか、説明も動画で行える。また、リアルのイベントと異なる点はイベント終了後もアーカイブとして残していけるというところだ。

VR教育ならではの難しさ
金谷建史氏が代表取締役を務めるテンアップは、VRコミュニケーションプラットフォーム「VR school」を運営している。小・中・高校生向けがあり、それぞれ子供たちの反応が異なるそうだ。
2016年からVR教育に携わってきたそうだが、最初に取り組んだのは塾の中に専用の部屋を用意したところからだった。そこでHoloLensを使い、歴史的な出来事を学べるように再現した。その後理科の実験ができるなど、様々なコンテンツを作っていったのだが、課題は1度体験したコンテンツは2度体験したがらなかったところだという。

ひとつひとつのコンテンツを作るのは現実的に難しかったため、現在はCG系の学校の中で授業を行っている。VRということで多くの人が面白がってくれるものの、VRならではの教材がないとただ面白いというだけで終わってしまう。今やっていることは、そうしたものを探して教材化していくことだという。
こうしたVRを使った授業は、当然のことながら遠隔でもできる。しかし、それでは塾の先生の仕事を奪ってしまうことにもなるのだ。しかし、現場の先生にVRを使った授業をしてもらうことで、モチベーションを下げることなくできる。同じVRも使い方ひとつで、現場でも印象も変わってくるというわけだ。

逆に、遠隔でも参加できることのメリットとしてVRを使ったオープンキャンパスがある。こちらは施設をVRで見るというよりも、コミュニケーションが取れることでモチベーションを上げることができるそうだ。
金谷氏が今回のコロナ騒動で感じたことは、VRを扱っている企業の多くがVR好きな人をターゲットにしているということだという。しかし、金谷氏が取り組んで来たのは学生向けということで、いわゆる一般の人向けともいえる。一般向けとイノベーター向けに展開するのとでは大きく異なるため、そこに差を感じるという。

バーチャル空間でのユーザー体験
ヤフーの水田千惠氏からは、最近のオンラインにおけるイベント体験と感情が揺さぶられた瞬間について紹介が行われた。ここ最近の状況からイベントのあり方も変わってきて、新たな気づきとして「バーチャル空間における実感が進化した」と水谷氏は語る。鍵となるのは、バーチャルな空間における客観的な視点だ。
世界観に没入しながら、観察する他者としての自分がいることが、実感を強めていると考えた。それを感じたきっかけとなったのは、バーチャルSNSの『cluster』を使ったイベントに参加したときだった。
参加者は全員ロボットのようなアバターで参加するのだが、そこで友達がいることを発見した。ほかのSNSではこうした状況は生まれにくいが、実際にバーチャル空間上で本人に近づいて挨拶することができる。こうした体験が新しいと感じたという。

これがリアルなアバターならさらにわかりやすいと考え、水谷氏は実際に自分のリアルアバターも作成している。その直後に、リアルアバターを使ってバーチャル空間で行われた美術イベントに参加したところ、自分がその場にいて作品を見ているのを客観視でき、その場に行っているような感覚があった。
そこにいる感覚以外に、リアルアバターで集まるとそばにいる感覚が生まれる。元々離れた場所からアクセスしても、その場にいるように感じることができるのだ。そうした場の共有をすることもできるのである。
バーチャルに入り込んで視野が狭くなるのではなく、あえて客観的に自分を見るという経験を加えることで実感が得られるようになるのだ。

このように、今回のイベントでは4人の登壇者から様々な事例を交えて、コロナ時代におけるVRの可能性について語られた。そこで、この状況だからこそ見えてきたものもかなり多いことがわかった。こうした体験を踏まえる前と後では、その後の展開も大きく変わっていったかもしれない。オンラインとVRなどのテクノロジーを組み合わせ、それをうまく活用していくことで、我々の生活もより豊かなものとなっていくことだろう。
Photo&Words 高島おしゃむ
コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。
雑誌の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の
企画・運用等に携わる。
その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。