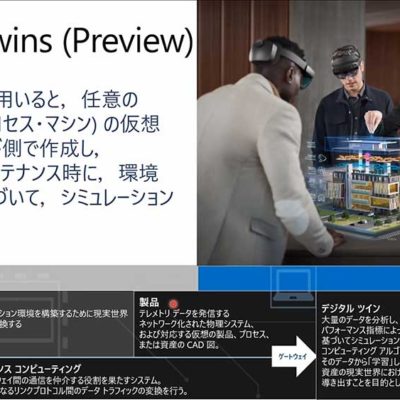05.22

【World MR News】AIは『バカの壁』を超えるか? 養老孟司氏が特別講演――「サイエンス映像学会 10周年記念大会」レポート②
5月12日に、早稲田大学小野記念講堂で「サイエンス映像学会 10周年記念大会」が開催された。本講ではその中から、初代会長を務めた養老孟司氏による特別講演「AIは『バカの壁』を超えるか?」 の模様をレポートする。
ちなみにタイトルではAIの話がメインのようになっていたが、特別なスライドなどは用意されておらずどちらかというとフリートークのようなスタイルで講演が進められていった。
■科学が進んでいくと全体像が見えなくなっていく
最近はカメラの中に「焦点合成」の機能が用意されており、動いていないものでも綺麗に撮影することができる。小さいものを撮影しようとすると、必ずどこかのピントがボケているものだが、この「焦点合成」の技術を使うことで、複数の画像からピントの合っているところだけをコンピューターで合成して、全体的にピントがあった写真にできるのだ。
養老氏は、これを20年以上前に初めてこの技術を見たときに驚いて「これはなんだろう?」と思ったという。顕微鏡で見るときは微動でピントをずらしながら、前に見た像をある程度記憶して自分の脳内で合成していた。それが合成された形で出てきたため、そう思ったのだ。自然のようであり人間が加工した画像でもある。
コンピューターで合成された画像は、医学の世界では当たり前となってきている。MRIやCTなどは、本来数字だが画像にしなければ医者も何を見ているのかわからない。一般の人は写真のように見ているが、これらは写真ではないのだ。
100倍の倍率の顕微鏡は簡単に使うことができる。だが、部屋の天井を100倍の倍率で見ると全体が100倍の大きさになる。つまり、精細な画像を見るというのは全体を考えると、とてつもなく膨大な情報を処理する必要があるのだ。逆に捉えると、細かい部分が繊細にわかると、その分全体がボケてくる。そのため、科学が進んでいくと全体像が見えなくなっていくと養老氏は語る。
昔、養老氏が分子のレベルまで見えるようになった電子顕微鏡で、人体全体を見たらどうなるか単純な計算をしたところ、足が地球で頭が月に行くサイズになったという。つまり、そのレベルで見ているということなのだ。しかし、こうした意識はほとんどの科学者にはなかったという。
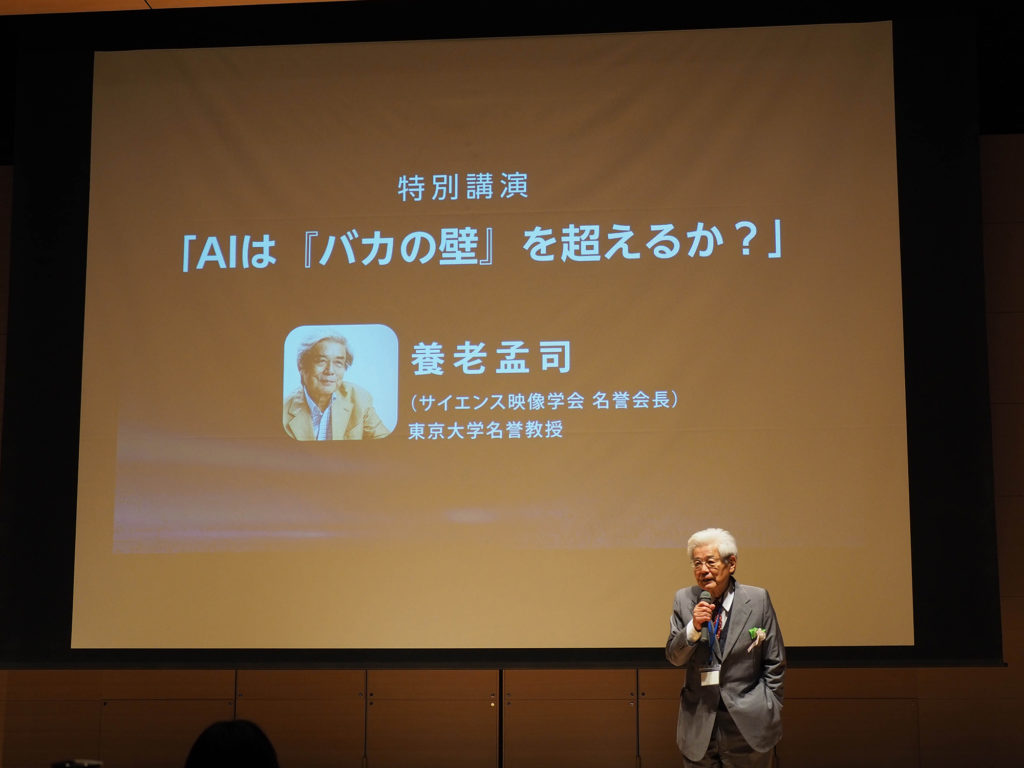
■コンピューターの時代で「本人」は「ノイズ」でしかない
コンピューターの世界を先行してやっていたのは、医学だと養老氏はいう。25年ほど前には、医者は患者の顔を見ずにコンピューターの画面を見るようになった。医者が見ているのでは患者の身体ではなく、検査結果という情報を見ているのだ。こうした傾向は医者だけではなく、銀行でも同様だ。
養老氏がある手続きをするために銀行を訪れたところ、本人確認の書類を持っているか聞かれたことがあった。養老氏は免許も持っておらず、まだマイナンバーカードもない時代で健康保険証も持ってきていなかったため、銀行員は「困りましたね。(本人だと)わかっているんですけどね」と答えたという。
ここで養老氏が考えた疑問が「本人とはなんだ?」ということだった。銀行が考えている「本人」とは違うのである。それから10年ほど経ち、新入社員が会社に入って半年ほど経ったきた頃、「あいつらメールで連絡してくるんだよ。仲間同士でもメールで話し合っているらしい」という話を聞き、そのときに「本人」を理解したという。
同じ部屋にいても顔を見て話すと、「二日酔いだな」とか「機嫌が悪いな」などいろんな情報が入ってくる。こうした情報はノイズでしかない。つまり、コンピューターの時代では「本人」は「ノイズ」でしかないのである。医療も同様だ。患者が持っている人間的なものを、徹底的に排除しているのである。それを機械で表せる計測できる形にしているのだ。
生の人間を見るということは、とんでもなくややこしいことだと養老氏は語る。ひと言でいうなら「複雑さ」や「多様性」となる。その時に置いていかれるのが、「感覚」だ。
東京のほとんどの建物は鉄筋コンクリートである。都会は、触覚を完全に拒否する社会である。触覚のほとんどはタブーとなっている。初めて行ったスナックで、隣に座った男性の手に触ると、ほとんどの場合逃げ出す。つまり、いろいろな意味で触ってはいけないのだ。
階段はあるが、歩くところはほとんど平らだ。時間によって日の高さも変わるが、建物にいるとわからない。わざわざそうした環境を作っていることに対して、つまらないと養老氏はいう。

■イコールを理解できるのは人間だけ
昨年、荒井紀子氏が『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』という書籍を出版している。その中の話で、簡単な4択問題が解けない子供たちの話が書かれていた。AIは当然のことながら解けるのだが、ひどいものでは正答率が20パーセントしかないものもあるという。ランダムで答えても25パーセントとなる正答率が、20パーセントになるのはわざと間違っているとしか思えないレベルである。
同書によると、読解力は中学生段階だけで伸びるという調査結果が紹介されている。これは言語を使った、単純な論理能力が中学生段階だけで伸びるということである。もちろん、個人差もあるため大人になってから伸びる人もいる。
養老氏は、この年代を「感覚から脳の中に入れ替わっていく最後の時期」と考えている。子供は感覚で生きているため、動物に近い。感覚が先行して中学生になり、一番問題となるのが数学で方程式が入ってくることだ。「x=3」という方程式が出てきたときに、これが気に入らない子供が出てくる。「xは文字」で「3は数字」だという認識から生まれるものだ。異なるものをイコールにすることに違和感を覚えるのである。なんでもなくこれらを通り過ぎる人もいる。
このイコールを理解できるのは人間だけである。チンパンジーでは理解することができない。チンパンジーにとっては、「A=B」であったとしても「B=A」ではないのである。なぜなら先に来るものが違うからだ。
そうしたことが先に頭に入ってくる子供は、そこから先に数学が進まなくなってしまうのである。かなりの子供が、「こんなもの解いてやるものか」と考えているのだ。でなければ、20パーセントという数字は出てこない。コンピューターに出来て中学生にできないのは当たり前の話で、「やる気がない」からなのである。

Photo&Words 高島おしゃむ
コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。
雑誌の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の
企画・運用等に携わる。
その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。