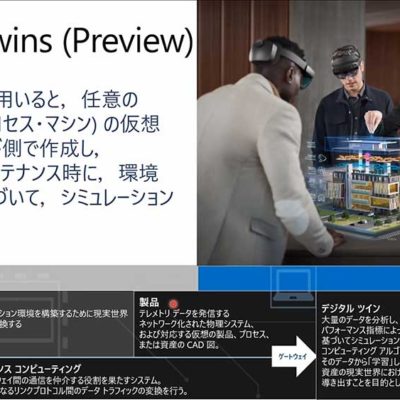02.04

【World MR News】水口哲也氏×稲見昌彦氏によるトークセッション「ARがもたらす身体の変化」――「ARISE#2 -Spatial Experience Summit-」レポートその③
2019年11月30日に、日本発のARコミュニティイベント「ARISE#2 -Spatial Experience Summit-」が開催された。本稿ではその中から、東京大学 先端科学術技研究センター教授の稲見昌彦氏とエンハンスCEOとシナスタジアラボを主催する水口哲也氏によるセッション「Augmented Human Session」の模様をお届けする。

▲写真左から稲見昌彦氏と水口哲也氏。
ARで600年ぶりの大革命が起こる
――拡張現実技術の普及で、人々の知覚能力はどのように進化していくと思いますか?
稲見氏:知覚というより認知のほうになるかもしれませんが、1990年ぐらいに米国心理学者のティモシー・リアリーが「バーチャル・リアリティは新しいドラッグだ」といってました。知覚の変化にはふたつ考え方があり、ひとつは人間の認知の解像度や同時に情報を処理する能力の方が、重要なスキルとして人間の方が新しく獲得していくというものです。こちらのほうが、AR時代には優秀とされる人になるかもしれません。
一方で、私が光学迷彩の研究を行っていたのは、ARは足し算ばかりしていくと、めちゃくちゃ見えづらくなっていくからです。実は引き算も大切なのではないか。現実世界から引き算する技術として、私は光学迷彩を開発していました。加減が出来て初めて調整ができるようになります。人間の認知フローに、ちょうどマッチングするぐらいの情報量や知識の量に減らしていくことがいいかもしれません。
人間の注意や意識のチャンネルを使うから、帯域があるんじゃないかという話しがあります。人間に知覚されないけど、人としてはそれによって行動が変容しているようなチャンネルを上手く使うことで、結果的に今あるARとはちょっと違ったシステムになります。何も気が付かないけど、何か問題が解決するというようなことをやっていくと、人間は新たな情報チャンネルを得たことになります。
水口氏:NTTドコモの岩村さんがおっしゃってた、500年後から見て今が大きな変革になるという意見に同意しています。人間本来の一番いい豊かな状況に戻って、それを超えていくというビジョンが見えます。
600年前に活版印刷が発明されました。それをテクノロジーやメディアと呼ぶこともできます。それにより情報が拡散して、今まで協会の中にしかなかった知識が一般の人に広まったことで、みんなの意識が高まりました。
130年前に映像が初めて生まれ、四角いフレームに白黒で音がなかったのが、音が付いてハイレゾになってきたけれども、未だに2Dで四角です。これは自然界の中には全くなかったもので、僕らの知覚は本来3Dで出来ているはずです。2Dの情報の窓や本など、不自然なものが入ってきています。
ARは、これを元に戻しつつもっと拡張できる時代に入ると思っています。600年ぶりの大革命が起こることを、僕も信じています。人間の感覚がどのように変わっていくかというと、共感覚的で3Dの世界にもう1回戻ることができるということなので、いろんなプラスが考えられます。ただ、やりかたを間違えると、とってもひどいことになります(笑)。そうならないようにすることをみんな考えながら、実験しつつ実装していくことになると思います。

稲見氏:ARを含めたXR技術は、活版印刷に匹敵するぐらいの新しいメディア技術です。それはなぜかというと、初めて体験やインタラクションを記録して再構成して連想することができるようになったからです。その一部が出来たのがゲームです。インタラクティブなものはなかなか固定できなくて、音楽とかも楽譜とレコードなど演奏を記録するものがないと完璧には再現できません。
水口氏:ゲームはまだ50年の歴史ですが、ゲームの役割はそろそろほかのものにマージしていくと思います。最初に生まれた体験メディアのひとつですが、ここから先は体験のメディアが起ち上がると思います。体験の送受信も体験の出版も可能になります。
10年後にグラスをずっとかけていなくても、必要なときにかけてというような生活をしていると、それがもう中心になるのは間違いないですよね。
ARを組み合わせると第3のコミュニケーションが生まれる
――拡張現実技術の普及で人々のコミュニケーションは、どのように変化すると思いますか?
稲見氏:ARを組み合わせると、第3のコミュニケーションが生まれます。第1は対面で、第2は「月が綺麗ですね」系ですね。第3は相手に乗り移って体験を共有することで、相手のことがわかるようになります。
誰かに憑依して一緒に作業をしていると、だんだん相手に親しみを感じてきます。これは変身型のコミュニケーションです。メディアアーテストの八谷和彦さんが最初に作られた作品は、視聴覚交換マシンです。これは、お互いに見ている世界を反転させるものです。そうすると、相手から見て自分が見るようになります。
そのときの八谷さんのチャレンジは、それでお互いにキスをしたらどうなるかでした。相手から自分はこう見えているんだとか、相手は自分のこういうところを見ているんだということがわかったそうです。これはまさに『君の名は。』の世界ですよね。お互いに入れ替わったからわかったじゃないですか。
自分が相手の立場になることで、相手のことがよくわかるようになります。VRで白人の女性が黒人の人にしばらく変身していると、無意識のうちの人種的偏見がなくなります。あと、アインシュタイン効果と呼ばれているもので、アインシュタインに変身すると知っている人は成績が少し上がります。まさにこれは、コミュニケーションのチャンネルがひとつ増える大きな質的な変化です。

水口氏:解像度がどんどん上がってレーテンシィもどんどん低くなっていくということを考えると、場所は確実に関係なくなります。共感性が上がって、「あ、あれってそういうことだったの?」ということも減り、気持ちの交換も起こってきます。ここがミソだと思っているのですが、現実の模倣するのはダメじゃないですか。それは大きなイノベーションではありません。対面しているのにそれでもグラスをかけるほうが、もっと気持ちが伝わるとかもっと知的なものが深まるなど、そうならないとダメなんじゃないかなと思っています。
稲見氏:シンプルなARでも無茶苦茶気持ちが伝わる可能性があります。ニコファーレってありましたよね。あそこは、(会場内の壁面がLEDになっており)いろんなコメントが流れるようになっていたんです。あれを見ていると、自分がエスパーになった気分になった感じがするんです。
日本人って、皆さんご存じのようにリアクションが薄いですよね。あまり発言もしませんが、「ネクタイが太い」などのコメントが流れてくるんですが、これはまさに皆さんが考えているけど口に出さないことです。会場にいる目の前の人は書いていないかもしれませんが、きっと頭の中でちょっと思ったけどいちいち発言しないようなこととかが、コメントで流れてきます。これはテレパシー感だと思いました。
――ウェアラブルでサジェストされて会話をするとき、どこまでが自分のコミュニケーション能力なのか疑問に感じることがあります。
稲見氏:一時期、日本の携帯小説はSFC(湘南藤沢キャンパス)の松井俊之先生に支配されていると言われていることがありました。増井先生は、昔ソニーコンピュータサイエンス研究所にいたときに、「POBox」と呼ばれる予測入力を開発しています。
予測入力で入力しているものを、パチパチ打っていくと文章になっていきます。ということは、携帯小説と言われているものの半分ぐらいは、増井先生の予測エンジンによって作られていることになります。そうなると、それは増井先生の作品なのか本人の作品なんだろうかと考えると、本人の作品になります。その延長で、会話のサジェスチョンも同じです。
「人生とは選択だ。何かを選ぶのと選ばないということ自体が人生だ」と増井先生がおっしゃっていたので、それ自体がその人の判断かなと思います。

ARを付けた人間はデジタルサイボーグだ
――拡張現実技術の普及で、どんな新しいビジネスが生まれてくると思いますか?
稲見氏:ARを付けた人間は、デジタルサイボーグと言えるんじゃないかと思っています。つまり、情報的に拡張されたサイボーグです。昔サイボーグ技術が1960年代に論文の中で示されたもので、宇宙で活躍するために臓器を埋め込むというのが原点です。あれはSFではなく論文だったんです。でも、我々はぜんぜん宇宙に行ってません。
その代わり、回りがサイバースペースなどARに囲まれています。そうしたときに、人間をデジタル的に拡張するというのが、AR的なものになります。いろんな研究者が人型ロボットを研究していますが、やはりめちゃくちゃ高価です。あれだけアクシエーターがあるものを、安くするのも限界があります。
そう考えると、そう簡単にヒューマノイドが広まるかわかりません。東大の暦本純一先生が「Human Uber」と言ってましたが、誰かが私に乗り移り3分間身体を貸します。そのときに、代わりに買い物などをするというものです。買い物途中で誰かに身体を委ねて、ついでに買って届けてあげるというようなことがあると、身体をプロキシーにできます。こうした、自分の身体を分貸しするようなビジネスが出てくるかなと思います。
水口氏:2Dで作られた過去のものは、そのまま生き残れないと思っています。ARが普通になった世界では、全部やり直しです。それは同じものを作るわけじゃなくて、昔はああいうものがありましたけど、ARの世界ではこうなりましたという感じのものがたくさん出てくると思います。なので、特定の何かというよりも全部オーバーホールなのかなというのが、僕の印象です。
昨日久しぶりに電車に乗りました。もう、びっくりしちゃって。社内に3連のモニターがあり、立っている間ずっと広告が見せられています。これは厳しいなと思って。何でこれでお金取るの? 逆に見なきゃいけないど、ただで電車に乗れるぐらいの話しじゃないかなというぐらい、どこもかしこも広告だらけです。これは、マツダ・ケイイチくんのディストピアの世界に近づいている気がします。東大の暦本先生はどうやって広告を消すかという・・・・・・。
稲見氏:AdBlock ARですね。
水口氏:それもなんだかな~。今までのやり方で広告を入れるのはやめようねと。まったく新しい広告の入れ方をARにどうやったら持ち込めるか。質的なものからイノベーションを起こせる人間が、次の時代のグーグルになるかもしれないですね。

デジタルが現実世界に溶け込むと危険な側面も出てくる
――今後拡張現実技術が複数の近く領域と結びついた時に、人はデジタルをどう捉えるようになると思いますか?
稲見氏:最近デジタルかバーチャルかというのを止めました。デジタルの世界も我々にとってはリアルです。起きている時間に、パソコンやスマホに向かっている時間は、社会人の方なら半分以上だと思います。そうなってきたときに、我々の生活そのもので仕事もその中に入っています。
デジタルはリアルかバーチャルの話しではなく、リアルです。そのリアルにインタラクティビティや複数の視覚領域というのが大切になってきます。現実感があると感じるのはふたつのキーがあります。ひとつは、各々のモダリティのクォリティです。視覚だったら視覚的に、より高解像度になることです。もうひとつは、人間は複数感覚で初めて答え合わせをしているんじゃないかということです。
初めて立体映像を見たときに、思わず手を伸ばしてしまいます。赤ちゃんはたいていのものを見て触って食べて五感で認識していきますが、我々は複数感覚が同期したときにそれは現実なんだと感じます。触覚は、現実感があると人が感じるのに大きな要素です。
ネイティブな人は、不便な物理世界よりコピペもできて光の速さで情報も送ることができるもうひとつの現実というようになるんじゃないかと思います。
水口氏:デジタルって超アナログってことなんですよね、きっと。これは拡張現実というよりも、世界の解像度が全体的に上がっていって分解度が上がっていって、量子化が起こってくるという流れです。そうなったときに、2Dではなく3Dで溶けていくという話しです。デジット化されて量子化されて、細かい粒度を持った状態で3Dの世界で生きるという話しです。
どう捉えるかというと、極めて自然になっているだろうし、それが自分の中でのリアリティになります。粒度が高まれば高まるほど、別なものという違和感としては見なくなってきます。危ない側面もあります。対面からふたり歩いてきたときに、ひとりはそこにいないけどすごい解像度で見えているという状況が絶対に起こります。そうした前提で、どうする? という話しはいろいろと出てくると思います。
他人に感覚を移すにはゼロ認証が大切
――複数の近くと結びついたARで、自分の感覚を他人にトレースしてまったく同じ感覚や感触を感じることは可能でしょうか?
稲見氏:感覚の種類によります。視覚だと比較的伝統的な分野なので、それに近いことは多数行われています。そこでよく言われているのが、ゼロ認証が大切だと言うことです。自分の身体というフィルターを通して、我々は情報を取っています。立体音響で頭部伝達関数(HRTF)というのが出てきますが、あれは頭と耳の形によって聞こえ方が変わってくるというものです。それにより、我々は3次元の音響を認識しています。
それをそのまま伝えてしまうと、自分の耳で聞いていない音になります。ダミーヘッドは、ある程度平均的な形にして出しているシステムです。そういう意味では、ある人の身体に入った情報を、いったん中立的な情報に逆フィルターをかけて戻してあげて、それを他者の身体に入れるということをする必要があります。
水口氏:まったく同じというのは厳しいですね。50はあると僕は思っています、人間の感覚が。もしかすると、もっとあるかもしれません。それを全部トレースするのは難しいですが、一部でも共感性はもたらすと思います。
聴覚でも、人間の耳は20kHz以上の音は聞こえないと言われています。しかし、確実に聞いています。ハイパーソニック・エフェクトの研究があり、熱帯雨林に行ったときに20kHz以上の音がたくさんあって、すごく落ち着きます。それはどこで聞いているかというと、身体の皮膚全体で聞いています。
そうしたものがたくさんあり、僕らは簡略化するために五感と非常におおざっぱにいってます。もっと分解していくほど、近づいてはいくけどすごく時間はかかります。その手前でもぜんぜん共感性はあるし、役割は果たしてくると思います。
稲見氏:水口さんにお伺いしたいのは、VRのゲームを作ってらっしゃって、ユーザーの体験はどこまでコントロール出来ているのでしょうか? ジェットコースター的VRだと比較的コントロールがしやすいですが。
水口氏:大雑把には出来ているんじゃないかなと思います。トレッキングやハイキングのコースを設定して、その通りに行くと主要なことは体験出来ます。そこで道草したり降りていったりしても大丈夫ですよという自由度もあります。でも、順番に行くと感動体験ができるように作ってあります。
稲見氏:山寺とかの設計ですね。ずっと登っていって、最後だんだん開けてくるみたいな。宗教的な聖地が高いところにあるのは、そこの体験の部分をデザインして共有しようというものだからです。そういう意味では、トレースというのは環境を含めてやったほうがいいのかもしれません。
――ありがとうございました!

Photo&Words 高島おしゃむ
コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。
雑誌の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の
企画・運用等に携わる。
その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。