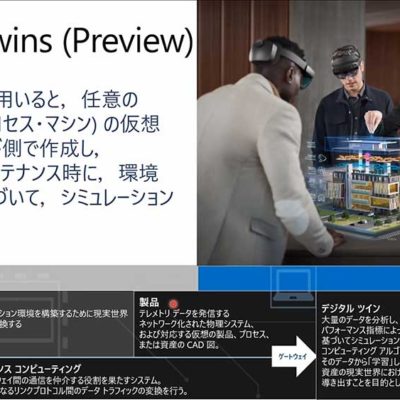09.03

【World MR News】優秀賞はPhotoshopで1年掛けて作った手書きアニメの「MOWB」が獲得! 「VRクリエイティブアワード 2019」レポート
VRコンソーシアムは、8月25日にデジタルハリウッド大学で「VRクリエイティブアワード 2019」を開催した。こちらは、これからのVR業界を牽引していく作品やクリエイターを発掘して、認知向上と活動の支援を目的に行われているものだ。2015年のスタートから数えて、今回で5回目のアワード開催となる。
2019年の応募作品は全部で73点。優秀賞(ビジネス部門)には5万円の賞金が贈呈されるほか、優秀賞と大川ドリーム賞のビジネス部門と学生部門にそれぞれ5万円が贈られる。

▲今回の「VRクリエイティブアワード 2019」受賞者と審査員。
■最優秀賞:『MOWB』
今回のアワードで最優秀賞に選ばれたのは、東京藝術大学大学院 映像研究家アニメーション専攻 Yuhara Kazuki氏の『MOWB』だ。これは、『Photoshop』を使い、1年間掛けて作られたという手書きアニメの作品である。Yuhara Kazuki氏には、賞金10万円とトロフィーが贈呈された。
Yuhara Kazuki氏「PhotoshopでVRを作っている人はあまりいないと思いますし、僕もそれしか方法を知らなかったため、このような形で作りました。評価をいただいて嬉しいです」

▲Yuhara Kazuki氏(写真左)
■優秀賞(ビジネス部門):『けん玉できた!VR』
優秀賞(ビジネス部門)を獲得したのは、CanRの『けん玉できた!VR』だった。こちらは、けん玉ができない人でもコンテンツを体験することでマスターできるという内容で、体験した満足度が高くVRとリアルを繋いだという部分が審査員から評価され受賞が決定している。
CanR 川崎仁史氏「ありがとうございます。もうひとつ嬉しいことがありまして、昨年VRでけん玉が上達する『けん玉できた!VR』を作ってきました。今日、『けん玉できた!VR』を通じて、新しくけん玉が出来るようになった方が1000人を超えました。このような賞もいただき心苦しいです」

▲川崎仁史氏(写真左)。
■優秀賞(学生部門):『地震列島VR』
優秀賞(学生部門)を受賞したのは、愛知工科大学板宮研究室 平川俊貴氏の『地震列島VR』だ。こちらは、日本全国で過去に発生した地震を、VRを通して体験出来るというコンテンツである。こちらは、トロフィーと賞金5万円が贈られた。
平川俊貴氏「毎日少しずつ作ったことで、このような賞をいただけたと思っています。ありがとうございました」

▲平川俊貴氏(写真左)。
■大川ドリーム賞
CSKの元会長である故大川功氏の意志を継ぎ、2011年に設立された「一般財団法人 大川ドリーム基金」。そこから生まれたのがこちらの賞だ。今回大川ドリーム賞として選ばれた作品は、Psychic VR Labの『STYLY』である。こちらには、トロフィーと賞金5万円が贈られた。
Psychic VR Lab 藤井明宏氏「『STYLY』はPsychic VR Labで作っている、VRのクリエイティブプラットフォームです。このような賞を取れたのは、プラットフォームを使ってくださるクリエイターの皆さんと盛り上がってくれているユーザーの方々のおかげです」

▲藤井明宏氏(写真左)。
■デジタルハリウッド賞:『memex「Cloud Identifier」Music Video + Virtual Creation Studio』
デジタルハリウッド賞は、memex + arsの『memex「Cloud Identifier」Music Video + Virtual Creation Studio』が受賞。トロフィーと賞金3万円が贈られた。
memex + ars「今回VRChatで作ったコンテンツが受賞したということで、UGCの時代が始められました。ここから時代の転換点になっていけたら嬉しいと思います」

■今後は「XR Consortium」として活動を継続
各賞が発表されたあと、VRコンソーシアム代表理事の藤井直敬氏より、VRコンソーシアムの名称が「XR Consortium」に変更されることが発表された。
これまで5年間活動を続けてVRコンソーシアムだが、5年前とは状況が変わり、VRという枠に閉じない様々なテクノロジーや表現が登場してきているというのが理由だ。

■豪華審査員によるパネルディスカッション
授賞式の前に行われたのが、審査員たちによるパネルディスカッションだ。登壇者は、ハコスコ 代表取締役 藤井直敬氏、デジタルハリウッド大学 学長 杉山知之氏、森美術館 館長 南條史生氏、東京大学 先端科学技術研究センター 教授 稲見昌彦氏、エンハンス 代表/EDGEof 共同創業者 水口哲也氏、エクシヴィ 代表取締役社長 近藤“GOROman”義仁氏、メディアアーティストの落合陽一氏、IntoFree 代表取締役 西川美優氏という豪華な面々である。
こちらでは、その一部を抜粋してご紹介する。
藤井氏:VRコンソーシアムが始まって5年です。始めた当初はハードウェアがなかったので、あるものを工夫して使っていました。ある意味、みんなの煩悩をそこに流し込むかという、コンテンツ力というか無茶苦茶なことをやられていました。
それが5年間たち、デバイスや開発プラットフォームが揃ってきて、ある意味GOROmanさんのような、凶器が溢れる人があまりいなくなりました。その分、裾野が広がってきたので、面白い時代になってきたなと思っています。VRコンソーシアムの皆さんは、5年間見てきたわけですが、一言ずつコメントをお願いします。
杉山氏:この5年間、もうちょっと全体的に進むのかと思っていたら、ゆっくりでした。それはヘッドマウントディスプレイが多くの人に使っていただけないということがあるので。ただ、VRという言葉が一般の人に定着したと思います。その中で、視覚と聴覚をやっていますが、研究機関では他の器官にも広がってきています。これからエンターテイメントとビジネスの産業で使っていくものと、徐々に進んでいく時間帯に入っていくと思っています。
南條氏:技術の開発をやっている部分が、産業にどう発展するか。それからアートやエンターテイメントなど、いくつかの方向があります。ビジネスがもって発展してもおかしくないと思っています。人間がやる必要がないところに、もっと出ていくハズです。アート系に関してちょっと弱いですね。あとはハードの発展がもっといかないと、被るのは重いし付けるの儀式のようです。それがメガネと同じようになってくると意味が出てくると思っています。

▲写真左から藤井直敬氏、山知之氏、南條史生氏。
稲見氏:私はこの5年間で思ったことは、よくバブルがはじけずに続いたなということです。Google Glassとかを付けている人たちがいましたが、あっという間にすっと消えてしまいました。それと比べれば、まだまだ残っています。アーリアダプターの次の次ぐらいに来ていると思います。
水口氏:90年代頭のムーブメントから、30年ほどたちました。そこからずっと信じ続けているひとりなので。この5年で、みんなの期待度は今がボトムです。ここからすごいことになるのは、みんなわかっています。それを支えているのは技術もそうだし、お金もそうですが、90年代に登場したときのパイオニアたちが「これはテクノロジーではない」と言い切ったことです。コンセプチャルに「そこにいる感覚をどう実現していくか」という、長いロードマップの話をしていました。やっとこれから面白い時代がやってくると思います。

▲写真手前左から、稲見昌彦氏と水口哲也氏。
GOROman氏:現状と課題ということで。現状は先に面白かったエピソードがふたつあるのでご紹介します。ひとつは、十代ぐらいの人が毎朝VRChatでラジオ体操をしているのがめちゃくちゃ面白くて。どこにいてもラジオ体操を、VRの中に集まってやっていてスタンプみたいなものがもらえるという話を聴きました。僕が小学校の頃にもそういうのがあったけど、それがVRの中でやれるんだと。僕が10代の時にパソコン通信にハマったのに、すごく近いなと思いました。
もうひとつは、「VARK」というVTuberのライブプラットフォームがあり、そのライブが2時から始まるので、それを見るためにOculus Questを持ってきました。課題はないかなと思ったんですが、今日「VARK」のライブを見るために会社に置いてきたOculus Questを取りに行ったことです。持ち歩いてないし家にもないので。将来的には常に携帯するポストスマートフォンになると思っています。
僕が思うのは、VRにハマっているのは、未来にみんながスマホを使わなくなって次のデバイスになったときの新しい体験を、今シミュレーションしているのかなということです。

▲GOROman氏。
落合氏:最近学生の作品を見てよく思うことですが、「日常からの距離の等差によってかき立てられる妄想力」というのがあると思うんです。『攻殻機動隊』を夢見ているときは、それと日常の距離が遠いから発生する妄想力。距離が近づくと、その妄想力は縮まっていて、陳腐になってしまいます。
メディアと向かい合うときには、入り口と出口が必要です。入り口は全天球カメラなどのコストダウン感が大きいです。出口としては、没入型ヘッドセットと透過型ヘッドセットの発達が大きいと考えると、比較的見半ばではあるもののモノは出てきて、モノが出てきたがゆえに日常からの妄想力の距離が近くなったので、コンテンツが弱まってきたなというのが実感です。
つまり、かき立てられた妄想力に近づいたから面白いと思っていたコンテンツが、実は手にメニューが出てくるのが楽しいかといわれると、全然楽しくありません。学生さんに何がやりたくてVRやるのと聞くと、「『ソードアート・オンライン』みたいに、空間にメニューが出てきて・・・」と答えます。メニューが出てくるのが楽しいのか? というのは重要な課題で、実現された妄想はそんなに面白くありません。
その割には、Apple Watchはみんな付けているし、儀式としてVRを付けるのも普通になってきました。感覚に手を入れないと、新しいコンテンツは出てこないのかもしれないと最近は思っています。しかし、脳に電極を刺すこと自体が面白いといっているうちは、おそらく面白いモノはでてきません。
その距離感がここ5年で変わり、コストが安くなってものすごく量が出てきました。メディアが陳腐化してもコンテンツがつまらなくなったわけではなく、ここで手を離さないのがポイントです。飽きっぽい人はここでやめてしまうので、やめないようにするにはどうすればいいかということを、我々は考え続けなければいけないと思っています。

▲落合陽一氏。
西川氏:仕事柄ハードウェアの普及台数をずっと見ています。2016年、2017年、2018年は、面白いぐらい売り上げが伸び、ハードウェアの普及台数も前年対比2倍ぐらい出ていました。今年に入ってから売り上げ台数は去年と変わらず踊り場に来ています。それは去年と同じぐらい売れているということで、市場に出ている台数は倍になっています。
安定してPS VRもOculus Questも出ています。一般の人がVRを知っていて、ボーナスが出たときに買おうと思っている人が世の中に結構います。それを見ていると、来年の市場はなくなりません。
ただ、5年前に言われていたように、すごいカーブで立ち上がりますということとは乖離が起きてきているのはたしかです。そのあとにまた来るモノに備えて、今ある技術とハードウェアでどれだけ良い物を作ることができ、これから登場するデバイスにそれをどう応用することができるかということを見据える必要があります。

▲西川美優氏。
GOROman氏:ちょっとヤバイと思ったのが、VTuberのライブを見るために買います。終わったら売りますと言ってた人がいたんですよ。それこそが課題だなと(笑)。
南條氏:コンテンツに引きずられて入ってくるなら、そのほうがいいんじゃないですか。そのほうが長く続くと思います。コンテンツを評価するために、ある技術を使って何をするかというと、開発する人と中身を作っている人が同じだと中身まで力が回らないときがあるんじゃないかと、僕は思っています。
藤井氏:技術を知っている人は、これ以上は出来ないことがわかるので、想像力がそこで止まるんですよね。そこでアーティストと一緒にやると、「これできないの?」と無茶なことを言い出すので。
南條氏:コンテンツをこうしたほうがいいという専門のライターのような人が、登場するんじゃないですかね、そのうち。
落合氏:わりかしメディアアーティストはそういう職業のような気はします。ただ、ストーリーが技術論に寄ったり深いコンテクストに寄ったりすると、一般的に共感不能になっていきます。
水口氏:自分は今興奮しているんですよ。ここから何が変わるかというのは、情報の組み合わせや横並びの制約の中での表現というところから、体験化するわけじゃないですか。その体験も、フレームを飛び越えてきます。現実や実際にあるものとの付合性が始まっていきます。
今までの経験があまり使えません。2次元の制約の中で磨いてきた演出論だったり、ストーリーテリングだったりするので。これが使えなくなるので、みんなスクラッチの状態でスタートラインに並びます。最初は混乱しますが、ここから先は、今までとはまったく違う「わーお」というものが、すごく出てきまし、その表現が求められてきます。そういう意味では、すごく面白くなると思います。
5年後や10年後は、まったく風景が変わっていると思います。みんな普通のARのグラスをかけて、結構な時間を使っているはずです。

GOROman氏:90年代VRブームのときに、ティモシー・リアリーが「VRは新しいLSD」というようなことをいっていました。私はLSDやったことはないですが、LSD的な体験になるぐらいの感覚的な刺激としてのモノは、まだ出来てないんじゃないかなと。
南條氏:『テトリス・エフェクト』はそっち系なの?
水口氏:僕もLSDとかはやったことがないので、わかりませんが(笑)。おっしゃるとおりだと思いますね。多分VRやARの、今のカレントテクノロジーに左右されない、もっとその先にある融合された世界の、幸せに生きていくビジョンはいったいなんだろうか? という議論に、早く行きたい感じがします。
南條氏:演劇や現代美術を見ていると、イマーシブな方向に行ってます。ニューヨークに有名な「イマーシブシアター」というのがあります。人がシーンに入っていき、演技している役者を2メートルほどの距離で見ています。ほかにも話題になった作品は、全部観客が中に入ってくタイプです。ようするに、空間体験が物語になっています。
VRはそれを作り出す装置でもあります。それに匹敵する新しい体験や経験、驚きがあるものは提供できていません。それは誰かが必ずやると思っています。
落合氏:中国の深センを歩いていると建物がピカピカしています。東京オリンピックは絶対これより小っちゃいなと思うわけです。そうすると、日本でメディアアートをやってできることは、盆栽を作ることぐらいです。
普段、イマーシブな仕事をしているから、それでより戻って地政学的なところを探すと、ヘッドセットの中は極めてソフトウェア的で、禅に近いです。禅に近いと、彫刻的、建設的、大規模的なもので物量戦で勝てないなら、モノの深みに行くしかありません。深まったモノのヘッドセットや、深まったモノとしてのメディアアートをずっと考えています。それは理解されるまでは、あと20年ぐらい掛かりそうだなと思いながらやっています。
でも、あと5年ぐらいしたら飽きてるんですが、その感覚をみていくと、今のイマーシブなところを追いかけて多様な人類がそれを受け入れるようになるまでの発火点は、もっと向こうだと思います。
水口氏:解像度のイマーシブと、解像度が絡まないイマーシブの両方があります。映画が三人称の芸術として発達してきたのはリニアで四角いからで、ぜんぜん解像度のないゲームみたいなものは、そんなものは取っ払って、三人称と一人称を行き来しながら、どう楽しいかということをやってきました。
解像度と関係ないところで、今を面白くやれるところとか、実験できることは結構あると思います。深センの高い解像度は、ビルが真っ白になってARを掛けて街を歩き始めるというように、真逆に行く可能性もあります。これが起こるのは、近いところで10年ぐらい先でもいろいろとあるだろうなという気がします。
落合氏:自発光型のパネルは、新しいモノだなと。深センとかのLEDパネルは、ARで駆逐されないと思っています。物質的に面白い点光源の集まりは、ガラス細工を見ているような気持ちです。僕はむしろ、あれを見ている人たちがセンシティブになるのかならないのかかが気になっています。水口さんほどセンシティブな人だと感じますが、一般人はそう感じないのでARなのか。「私はLEDパネルじゃないとテンション上がらないの」という人が出てくるのかが重要です。
水口氏:まぁ、ミックスでしょうね(笑)。渋谷の街もすごいことになってますよね。実験で巨大なLEDが点灯していましたが、あまりにもまぶしすぎてあまり気分が良くなかったです(笑)。なので、ミックスになってくるんだろうなと思いました。

Photo&Words 高島おしゃむ
コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。
雑誌の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の
企画・運用等に携わる。
その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。